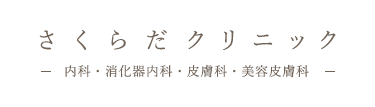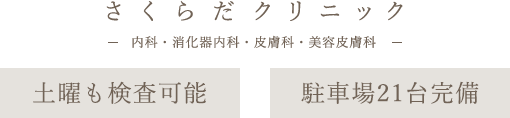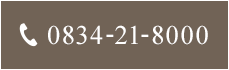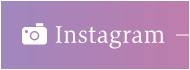ピロリ菌とは
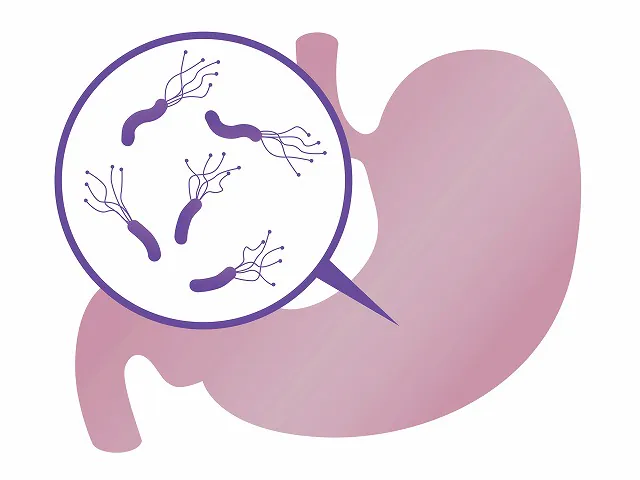 正式にはヘリコバクター・ピロリという名前で、両端にはヒゲとシッポを持つ長さ2.5~5μm程度の大きさの細菌です。胃内に感染すると、ウレアーゼという酵素を出して自分の周りにアンモニアを生成し、胃酸を中和して住み着きます。それによって胃内は常に炎症を起こした状態になり、胃潰瘍、胃がん、十二指腸潰瘍などが発症しやすくなります。WHOの外部組織である国際がん研強機関(IARC)は、世界的に見て胃がんの8割程度がピロリ菌によって引き起こされたものと報告しています。
正式にはヘリコバクター・ピロリという名前で、両端にはヒゲとシッポを持つ長さ2.5~5μm程度の大きさの細菌です。胃内に感染すると、ウレアーゼという酵素を出して自分の周りにアンモニアを生成し、胃酸を中和して住み着きます。それによって胃内は常に炎症を起こした状態になり、胃潰瘍、胃がん、十二指腸潰瘍などが発症しやすくなります。WHOの外部組織である国際がん研強機関(IARC)は、世界的に見て胃がんの8割程度がピロリ菌によって引き起こされたものと報告しています。
過去には汚染された生水を介して伝染するとされていましたが、現在、水道水などの衛生環境が整った日本では、生水経由の感染はほとんど見られず、保菌者の親から幼児期に口移しで食べさせてもらうことなどが、原因として考えられています。
除菌治療
ピロリ菌に感染していることが分かったら、除去治療を行います。まずは1回目の除菌治療として、クラリスロマイシン、アモキシシリンという2種類の抗生剤と、その効果を高めるための胃酸分泌を抑制する薬としてタケキャブ(またはPPI)の3種類の薬がセットになったものを7日間、毎日2回ずつ服用します。1回目の除菌治療での成功率は感染している菌が、クラリスロマイシンの耐性菌であるか否かによって少し変わりますが、最近になって新しい作用メカニズムで胃酸の分泌を抑制するタケキャブが登場したため、除菌率が上がり、約80~90%とされています。
7日間の服薬の後、1月ほどをおいて除菌成功か否かを判定する検査を行い、成功であれば治療完了、失敗であれば2回目の除菌治療を始めます。2回目は抗生剤のクラリスロマイシンをメトロニダゾールという抗菌薬に変更して3種類の薬を同様に服用します。服用終了後同様に1月ほどおいて除菌判定を行います。ここまでの治療で約99%除菌が成功すると言われています。
ピロリ菌の除菌は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんといった疾患の発症リスクを下げ、ご自身にとっても有用なだけではなく、子世代への感染を防ぐ意味でも大切です。ピロリ菌の検査と2度目の除菌治療までは、慢性胃炎などの症状さえあれば健康保険適用で受けることが可能ですので、一度は検査を受け、感染が判明したら積極的に治療を行ってください。
ピロリ菌感染検査
ピロリ菌の感染検査は、胃カメラ検査の際に行うものと、胃カメラを使わない検査がありますが、健康保険適用の除菌治療を受けるためには、胃カメラ検査による確定診断や胃バリウム検査による胃潰瘍・十二指腸潰瘍の診断が必要になります。
胃カメラ検査を受けない感染検査のみをご希望の際は自由診療となります。
胃カメラ検査時に行う感染検査
胃カメラ検査を行う際に、ピロリ菌による炎症と推定される特徴的な病変部分を採集して検査を行う方法です。
迅速ウレアーゼ試験
ピロリ菌は自らが分泌するウレアーゼによってアンモニアを生成し、胃酸を中和しています。そのため、採集した組織がウレアーゼによってpHに変化が見られるかどうかを、試験薬で測定し、間接的に感染の有無を確認する方法です。
鏡検法
採集した組織を顕微鏡下で、肉眼で観察することによってピロリ菌感染の有無を確認します。
培養法、薬剤感受性試験
採集した組織をすり潰して、培養地に数日置いて感染の有無を確認する方法です。菌株を特定したり、抗菌薬耐性を調べたりすることも可能ですが、結果が出るまで4~5日かかります。
胃カメラ検査以外で行う検査
尿素呼気試験(UBT)
ピロリ菌は、ウレアーゼという酵素を分泌し、体内の尿素を二酸化炭素とアンモニアに分解します。自然界に存在する炭素はほとんどが炭素12(12C)というものです。そのため通常ピロリ菌が分解して呼気に含まれる二酸化炭素中の炭素は98.9%程度12Cになります。そこで、この尿素中の炭素を、自然界にほとんど存在しない同位元素である炭素13(13C)に置き換えた薬を飲んで、しばらくしてから呼気を測定します。もし胃の中にピロリ菌が存在して、この特殊な薬剤の尿素を分解すると、呼気に含まれる二酸化炭素中の13Cの分量が増えるため、感染が判明する仕組みです。
抗体測定法
血液や尿、唾液などからピロリ菌に対する抗体の有無を測定する方法です。
便中抗原測定法
いわゆる検便検査で、胃の中のピロリ菌が糞便中に排泄される性質を利用し、便中のピロリ菌の抗原を測定します。
ピロリ菌感染検査の
健康保険適用
ピロリ菌感染検査は、以前は潰瘍などの症状が無ければ保険適用されませんでしたが、2013年以降慢性胃炎の症状があれば、健康保険が適用されるようになりました。慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの症状があり、胃カメラ検査を受けて、ピロリ菌陽性と判定された場合、健康保険適用による検査・治療が可能になります。
半年以内に人間ドックなどで
胃カメラ検査を受けた方へ
慢性胃炎によるピロリ菌感染検査・除菌治療が健康保険適用になったことにより、半年以内に胃カメラ検査を受診し、慢性胃炎と診断された場合には、ピロリ菌感染検査に健康保険が適用されることになりました。
自費診療となるピロリ菌
検査・除菌治療(ピロリ菌3回目除菌費用)
 ピロリ菌感染検査と除菌治療に健康保険を適用するためには、胃カメラ検査による慢性胃炎、その他の上部消化管症状の確定診断が必須です。そのため、胃カメラ検査による確定診断や胃バリウム検査による胃潰瘍・十二指腸潰瘍の診断が必要になります。
ピロリ菌感染検査と除菌治療に健康保険を適用するためには、胃カメラ検査による慢性胃炎、その他の上部消化管症状の確定診断が必須です。そのため、胃カメラ検査による確定診断や胃バリウム検査による胃潰瘍・十二指腸潰瘍の診断が必要になります。
なお、これはあくまで確定診断として胃カメラによる検査で慢性胃炎やその他の疾患があると判定されたという経緯が必要なだけです。除菌治療後の除菌判定に胃カメラ検査が必要であるという意味ではありません。
また、除菌治療においては、2回目までが健康保険適用の対象で、3回目以降は自由診療となります。
さらに除菌治療に使用する抗菌薬・抗生物質も1回目除菌ではクラリスロマイシン(商品名クラリス)、アモキシシリン(ペニシリン系抗生剤)と決められていますので、それ以外の抗生剤、抗菌薬を使用した場合、保険適用外となりますので注意が必要です。
アレルギー等の事情でペニシリン系(アモキシシリン)などの薬剤が使用出来ない場合は、健康保険適用外とはなりますが、その他の抗菌薬もありますので、ご相談ください。
ピロリ菌3回目除菌費用
診察・検査:15,000円
別途薬剤料:8,000円前後
除菌治療の流れ
まずは胃部の症状がある場合、胃カメラ検査を実施した際に、組織を採集し、ピロリ菌感染判定検査を行います。陽性反応が出れば、健康保険による除菌治療が可能です。
1薬剤の服用
ピロリ菌を除菌するため第1回目の除菌治療としては、クラリスロマイシン、アモキシシリンの2種類の抗生剤とタケキャブ等のPPIなどの胃酸分泌抑制薬、第2回目の除菌治療としてはクラリスロマイシンをメトロニダゾールに変更した除菌キットを7日間、毎日1日2回服用します。これらは、除菌キットとして、1回分ずつセットにした薬剤の形で提供されています。
起こる可能性のある副作用
これらの薬剤によって、味覚異常(約30%)、下痢(13%)、蕁麻疹(約5%)、肝機能障害(約3分%)の副作用が起こることがあります。
副作用を感じたら、それに応じた対応を致しますので、すぐに当院までご連絡ください。全身で2箇所以上の部分でアレルギー反応が起こるアナフィラキシーや、呼吸困難などのアナフィラキシーショックの症状が出た場合は直ちに服用を停止して、受診してください。
2除菌判定
7日間の服用を完了して最低でも1か月経過しなければ正確な除菌判定が出来ません。
除菌判定で陰性であれば治療完了です。1回目の除菌成功率は、クラリスロマイシン耐性菌が多いため、一時は7~8割と言われましたが、新しい胃酸分泌制御薬のタケキャブの登場によって、その成功率が9割程度まで上がったとされています。
もし除菌に成功していなかった場合は2回目の除菌治療に移ります。
32回目の除菌治療
1回目の除菌失敗は、クラリスロマイシン耐性菌の可能性が高いため、2回目はクラリスロマイシンをメトロニダゾールに変更して同じ治療を7日間行います。
42回目の除菌判定
2回目の7日間服用が完了しておよそ2か月後に、除菌判定検査を行います。この時点でも除菌に失敗した場合、3回目の除菌を行いますが、3回目からは自由診療扱いとなりますので、ご注意ください。なお1回目、2回目を合わせた除菌成功率は99%程度とされています。