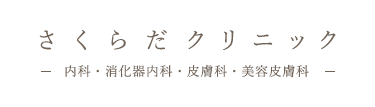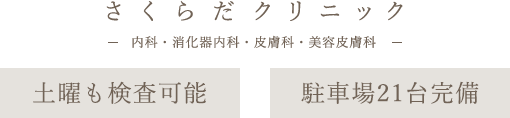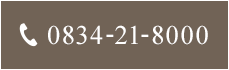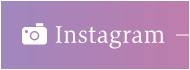下痢とは
 下痢は、便の形状が保てず、水のように柔らかくなるため、水様便と表現されます。通常のしっかりとした形の便は、食物の残滓に大腸で吸収されなかった水分が70~80%残っています。これが、さらに水分が残って80~90%程度の状態を軟便、水分が90%超えたものを水様便となり、下痢の場合、軟便または水様便に加えて、便の量や回数が通常の状態より増加し、腹痛など腸の不快な症状を伴っているものを言います。
下痢は、便の形状が保てず、水のように柔らかくなるため、水様便と表現されます。通常のしっかりとした形の便は、食物の残滓に大腸で吸収されなかった水分が70~80%残っています。これが、さらに水分が残って80~90%程度の状態を軟便、水分が90%超えたものを水様便となり、下痢の場合、軟便または水様便に加えて、便の量や回数が通常の状態より増加し、腹痛など腸の不快な症状を伴っているものを言います。
原因としては、大腸で上手く水分を吸収出来ない、粘液などの分泌物が増えている、ぜん動運動が亢進して大腸を通過する時間が速くなり過ぎているという3つの要素が考えられます。
急激に症状が起こり、1~2週間以内に症状が治まっていく場合を急性下痢、3週間以上症状が続く場合を慢性下痢と分類します。
急性下痢は、ほとんどの場合がウイルスや細菌による感染性の下痢で、その他には冷えや服用している薬の副作用などの場合もあります。一方で慢性下痢は、消化管の機能に異常が起こっている場合や、何か原因となる疾患、慢性的な炎症などが起こっている場合もありますので注意が必要です。
早期の受診が必要なケース
下痢に加えて、発熱、悪心(吐き気)・嘔吐、血便・粘血便、冷や汗・めまい・頻脈などの脱水症状が起こっているような場合は、早急に受診してください。特に下痢の場合、上手く水分を補給出来ないと脱水を起こし、重度になるとショック症状に至ることもあります。また、脱水から腎不全を起こす可能性もあります。水分を摂取しようとしても吐き戻してしまったり、すぐに下痢となって出てしまうようなケースで、上記のような症状の他に、尿の色が濃くなってきたり、あまり尿が出なくなったりする場合は救急対応も含めて、すぐに受診してください。
日常的な原因による下痢
食べ過ぎ・飲み過ぎ・刺激が
強い香辛料
 暴飲暴食や辛い刺激物の摂り過ぎは、胃酸の分泌が増えることによって、粘膜が刺激され腸のぜん動運動が亢進してしまいます。それによって大腸での食物の滞留時間が減り下痢になります。
暴飲暴食や辛い刺激物の摂り過ぎは、胃酸の分泌が増えることによって、粘膜が刺激され腸のぜん動運動が亢進してしまいます。それによって大腸での食物の滞留時間が減り下痢になります。
冷え
 冷たい飲食物を多く摂ると、消化管の周辺も冷えてしまうことで血行が悪化します。そのため十分に腸が活動出来なくなり、下痢を起こします。
冷たい飲食物を多く摂ると、消化管の周辺も冷えてしまうことで血行が悪化します。そのため十分に腸が活動出来なくなり、下痢を起こします。
ストレス
 腸は脳との関係が密接で、自律神経によってバランスを取りながら活動しています。ストレスや疲労などによって自律神経が乱れることで、腸が痙攣を起こし下痢になります。また、下痢と便秘を繰り返す仕組みも、自律神経の乱れによってぜん動運動が亢進したり低下したりを繰り返すことによるものと考えられています。
腸は脳との関係が密接で、自律神経によってバランスを取りながら活動しています。ストレスや疲労などによって自律神経が乱れることで、腸が痙攣を起こし下痢になります。また、下痢と便秘を繰り返す仕組みも、自律神経の乱れによってぜん動運動が亢進したり低下したりを繰り返すことによるものと考えられています。
疾患の症状として現れている下痢
感染症
一般的に下痢で最も多く考えられるのが、ウイルスや細菌などの病原体による感染症です。
ウイルスでは、ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどが多く、細菌ではサルモネラ菌、O-157などの病原性大腸菌によるものなどです。夏場は細菌感染が多く、冬場はウイルス感染が多いと言われています。
急激に、激しい下痢、腹痛や発熱、嘔吐といった症状が起こり、脱水を起こしやすいため早急な治療が必要です。
過敏性腸症候群
下痢や便秘、腹部膨満感などが続き、検査を受けても原因となる疾患は見つからない場合、腸機能に異常を起こしている過敏性腸症候群が疑われます。ストレスなどをきっかけにして、突然の腹痛と共に下痢を起こす下痢型や、下痢と便秘を繰り返す混合型、便秘が続く便秘型、腹部膨満感などを起こす分類不能型に分かれます。
気分の問題ではなく、腸機能に異常を起こしていることが原因で、日常生活に支障を来しやすいため、適切な治療が必要です。
潰瘍性大腸炎・クローン病
慢性的な消化管の疾患で、炎症が続き、下痢や便秘を起こします。炎症性腸疾患(IBD)としてこの2つの疾患は同系列と考えられ、どちらも活動期(再燃期)と寛解期を繰り返し、症状は似ていますが、潰瘍性大腸炎は症状が大腸に限定的で、クローン病は口から肛門まで消化管全体に症状を起こすところが異なります。どちらも原因が不明で難治性のため厚生労働省によって難病に指定されていますが、適切な治療によって、元の日常生活を送ることも可能になってきています。
大腸ポリープ・大腸がん
大腸がんや大腸ポリープは、共に初期の状態では自覚症状はほとんどありません。しかし進行してくると、大きくなって便の通りを妨げるため、下痢と便秘を繰り返すような症状が現れることもあります。また、出口近くの硬い便が通る場所では、便が擦れて出血し血便や便潜血となることもあります。
アレルギー性胃腸炎、乳糖不耐症
特定の食物や薬物などがアレルゲンとなって、下痢などを引き起こすことがあります。予防のためには、アレルゲンとなる物質を避けることです。
乳糖不耐症はアレルギーとは異なりますが、牛乳に含まれる乳糖(ラクトース)の分解酵素を持たない、あるいは不足しているために腹痛や下痢を起こします。
下痢予防
食事
 食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎは下痢の原因となります。適度な飲食を心がけましょう。また、強い香辛料なども胃を刺激し胃酸分泌が増えるため、腸粘膜も刺激され下痢を起こしやすくなりますので、控えめにしましょう。
食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎは下痢の原因となります。適度な飲食を心がけましょう。また、強い香辛料なども胃を刺激し胃酸分泌が増えるため、腸粘膜も刺激され下痢を起こしやすくなりますので、控えめにしましょう。
ストレス
腸と脳の深い関係を取り持っているのが自律神経です。自律神経がストレスや過労で乱れると、腸の動きのコントロールが上手く働かなくなって下痢や便秘を起こしやすくなります。規則正しい生活を心がけ、オフの時間は出来るだけリラックスしてストレスなどを溜めないように気をつけましょう。
節煙・禁煙
喫煙によるニコチン摂取は、腸のぜん動運動を促進する効果があります。そのため下痢を起こしやすくなる人もいます。喫煙しない人にまで健康被害を広げる可能性もありますので、禁煙が望ましいですが、少なくとも節煙を守ってください。