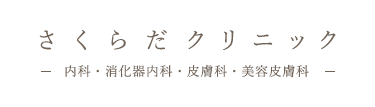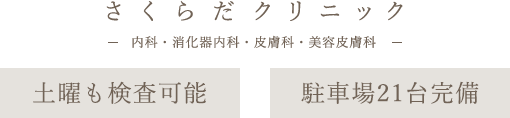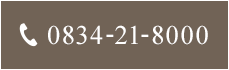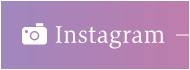げっぷやおなら
 げっぷもおならも、食物と一緒に飲み込んでしまった空気や炭酸飲料による二酸化炭素、消化管内で発生したガスなどが排出される、人体に備わった自然な機能の一つです。げっぷは発生したガスが口から排出されるもので、おならは肛門から排出されるものです。
げっぷもおならも、食物と一緒に飲み込んでしまった空気や炭酸飲料による二酸化炭素、消化管内で発生したガスなどが排出される、人体に備わった自然な機能の一つです。げっぷは発生したガスが口から排出されるもので、おならは肛門から排出されるものです。
どの程度の回数や量が出るかについては、個人差が大きく、一概には言えません。ただ、普段よりずっとげっぷやおならの回数が多い、それと共に膨満感などの不快感を伴うようになった、げっぷやおならが出そうで出ないなどの他の症状も出てくると、何らかの疾患によって胃腸内のガスが増えている可能性もあります。げっぷやおならがあまりに多い場合、日常生活の質が低下してしまいます。お悩みの方はいつでもご相談ください。
受診が必要なげっぷやおなら
以下のような症状がある時は、お早めに消化器内科を受診してください。
- 胸焼け、すっぱい物が一緒に上がってくる、咳などを伴うげっぷ
- 腹痛を伴い、下痢・便秘などの排便症状があるおなら
- げっぷやおならの回数が普段より明らかに増えている
- げっぷやおならが出やすい状態が長期間続いている
- げっぷやおならが出そうなのに出ず苦しい、膨満感がある など
げっぷやおならが
増える原因
よく噛まずに食べ物を飲み込んでしまう早食いや炭酸飲料の飲み過ぎなどで体内に空気を多く取り込むとげっぷやおならが増える傾向があります。また、前屈みの姿勢、きついベルトやお腹を締め付ける下着などもげっぷが増える傾向があります。
また、食事のバランスが偏り、食物繊維などを摂り過ぎることや、ストレス、過労など生活習慣の乱れなどによって腸内フローラが変質してしまうと、腸内で発生するガスが増えてげっぷやおならが増える傾向があります。
げっぷやおならの症状が
現れる消化器疾患
げっぷが増える消化器疾患
食道裂孔ヘルニア
胸郭と腹腔を隔てている薄い筋肉の膜である横隔膜には、食道を通すための食道裂孔という穴が空いています。何らかの理由でその部分から胃が胸郭内へ飛び出してしまうと、逆流性食道炎を起こしやすくなり、げっぷが増えることがあります。
逆流性食道炎
強い酸性の胃液を含んだ胃の内容物が食道に逆流し、炎症を起こしている状態です。胸焼け、心窩部痛に伴い、げっぷ、呑酸(すっぱい物が上がってくる)、咳、のどの違和感などが起こります。
機能性ディスペプシア
胃痛、胃もたれ、げっぷ、少し食べただけでお腹がいっぱいになるなどの症状が起こり、検査をしても、特に原因となるはっきりとした疾患が見当たらないのが機能性ディスペプシア(FD)です。上部消化管のぜん動運動や胃酸分泌などの機能に問題があって起こっていると考えられています。
呑気症
人は誰でも、食事の際などに多少の空気は一緒に飲み込むものです。しかし、呑気症は食事以外の日常生活の中でも空気をたくさん飲み込んでしまうことから起こる疾患で、空気嚥下症と言われることもあります。それによって、消化管内に空気が溜まってげっぷやおならが出やすくなる他、膨満感、胸焼け、悪心などが起こります。猫背の方や緊張すると唾を飲み込むような癖のある方などに起こりやすい疾患です。
おならが増える消化器疾患
機能性便秘
便秘にも様々なタイプがありますが、腸のぜん動運動が低下して、直腸へと送り出す力が不足してしまうことで起こるのが機能性便秘です。腸内で便が滞留するため、ガスが発生しやすく、おならが増え、膨満感や食欲不振などが起こります。便秘は慢性化することで大腸疾患を誘発しやすくなりますので、注意が必要です。
過敏性腸症候群
腹痛、お腹の不快な症状などがあって検査を行っても、はっきりと原因となるような疾患が見つからず、症状だけが存在するのが過敏性腸症候群です。下痢型、便秘型、下痢と便秘を交互に繰り返す混合型、腹部膨満感などが主な症状の分類不能型の4タイプがあります。いずれも腸のぜん動運動や内分泌などの機能が障害されることで起こると考えられており、症状としておならが増える場合があります。
呑気症
呑気症は食事以外の日常生活の中でも空気をたくさん飲み込んでしまうことから起こる疾患で、空気嚥下症と言われることもあります。それによって、消化管内に空気が溜まってげっぷやおならが出やすくなる他、膨満感などの症状が起こります。緊張すると唾を飲み込むような癖のある方などに起こりやすい疾患です。
おならが出なくなる疾患
腸閉塞
手術痕などの癒着や、腸の疾患などで、腸管が塞がってしまうのが腸閉塞です。そこから先へ食物やガスが通らなくなり、詰まってしまうため、腹部膨満感があり、おならも出なくなってしまい、激しい痛みなどの症状が起こります。緊急に医療機関を受診してください。
げっぷやおならの検査
 問診で、どのような症状がいつ頃から続いているのか、既往歴、服薬中の薬、生活習慣などを詳しくお訊きして、必要と考えられる検査を行います。
問診で、どのような症状がいつ頃から続いているのか、既往歴、服薬中の薬、生活習慣などを詳しくお訊きして、必要と考えられる検査を行います。
炎症が疑われる場合、血液検査、胃カメラや大腸カメラ検査などを行います。また、お腹のガスの状態を調べるため腹部X線検査や腹部超音波検査を行うこともあります。腹部超音波検査に関しては、腸閉塞が疑われる場合の簡易検査としても行うことがあります。
特に内視鏡検査に関しては、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医である医師が、高性能な内視鏡システムを駆使して、スピーディーでありながら正確な検査を行っています。どうしても内視鏡検査が苦手という方には、鎮静剤をつかってうとうとと眠っているような状態のまま検査を完了出来る方法もあります。安心してご相談ください。
げっぷやおならの症状で
お悩みの方へ
 げっぷやおならはその回数だけではなく、臭いが気になる方も多いのではないでしょうか。特におならの臭いは、食事の内容によって強くなってしまうことがあります。例えば肉類などたんぱく質の多い食物、またニンニクなど匂いの強い食物も消化されるとアンモニアや硫化水素を発生させやすく、おならの臭いが気になる時は控えめにすると良いでしょう。
げっぷやおならはその回数だけではなく、臭いが気になる方も多いのではないでしょうか。特におならの臭いは、食事の内容によって強くなってしまうことがあります。例えば肉類などたんぱく質の多い食物、またニンニクなど匂いの強い食物も消化されるとアンモニアや硫化水素を発生させやすく、おならの臭いが気になる時は控えめにすると良いでしょう。
さらに腸内フローラの変質によってげっぷやおならが出やすくなってしまうことがあります。その場合は、乳酸菌や酪酸菌の多い食べ物や飲み物を摂ることで腸内フローラを整えることが出来ます。
当院は、げっぷやおならの症状の一つの、臭いについてのお悩みにも対応しています。お気軽にご相談ください。